こんにちは、@ポジりすです!
「最近よく見る『アフターデジタル2 UXと自由』っていう本を買うか迷うなー」、「『アフターデジタル2 UXと自由』の本を読んで変わったことを知りたい」と悩んでいませんか?
このような方に、今回は、「『アフターデジタル2 UXと自由』から学べる3つのこと、読むべき人」について、記事を書きました!
ちなみに、私はアフターデジタルも読んでおり、以下で感想書いています。

- 『アフターデジタル2 UXと自由』から学んだ3つのこと
- この本を読むべき人と読まなくていい人
- Twitterから他の声を抜粋し、リアルなレビューがわかる

こんな内容を解決できる記事を作成しました!
僕は現在社会人2年目で、IT企業でSEとして働いています。
簡単な自己紹介をさせていただくと、現在「独学で、社会人の生活を豊かに!」をテーマにブログでさまざまな話題を発信しています。
今回、自己理解を深めるために買った、「アフターデジタル2 UXと自由」を読んだので、この本の感想を書いてみました。少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです!
※この記事では、本の要約は記載しておりません。本の要約を知りたい方は、以下のflierで完璧な要約が書かれておりますので、そちらをご利用ください!!今なら7日間無料なので、ぜひお試しください!!
結論、「アフターデジタル2 UXと自由」については以下の学ぶことがあり、以下の方におすすめです。
学べること
[第1位] OMOとO2Oの違いから学ぶ、OMOの真の目的 [第2位] 日本のデジタル対応の落とし穴 [第3位] DXの社内説得方法
おすすめの方
・アフターデジタルを読んで「読んでよかった」と思った方
・DXについて深く知りたい方
・データをどう戦略に活かすかを学びたい方

この本は、大ヒットしたアフタ=デジタルの続版で、多くの人に薦められています。
Amazonでは800の評価数を超え、星4.3と高評価となっています。(2022年2月現在)
アフターデジタル2 UXと自由 から学んだ3つのこと

アフターデジタル2 UXと自由から学んだ3つのことを紹介します!!
[第1位] OMOとO2Oの違いから学ぶ、OMOの真の目的
本書のタイトルであるアフターデジタルは、
行動データを高頻度で取得できるような世の中では、データ化できないオフライン行動がなくなり、「オフラインがデジタル世界に包含される世界」のことと定義されています。
そんなアフターデジタルの世界の中で、アリペイなどの中国の最先端の事例を紹介しながら、どうビジネスを展開すべきかを解説しています。
その中で僕が1番印象に残ったことは、OMOとO2Oの違いから学ぶ、OMOの真の目的の箇所です。
僕は、社内でよくOMOとO2Oの言葉を耳にしていたのですが、なんとなくしか理解しておらず、本質を知りませんでした。
しかし、この本を通じて、自分が目指すべき方向がはっきりしたので、少し紹介します。
本著では、OMOをこう定義しています。
O2O、考えそのものが「オンからオフに誘導する」という企業目線であり、基本は購買や成約をゴールとした思考です。一方のOMOは、そもそも「ユーザーはそのとき一番便利な方法を選びたいだけであり、オンラインとオフラインといったチャネル概念で分けていないので、それに合わせてジャーニーで考えよう」という意味合いです。顧客目線をベースにしていますし、
アフターデジタル2 UXと自由| 藤井 保文 (著)
このように、O2OとOMOの一番違う点としては、O2Oが企業目線であるに対して、OMOは顧客目線であることです。
OMOは、あくまで顧客提供価値を増幅するための考え方というのが、新たな学びでした。
オンラインとオフラインの単なる連携するシステムを構築するのではなく、ユーザの体験価値を最大化するサービスを考えようと思いました。
[第2位] 日本のデジタル対応の落とし穴
この本を読んで学んだこと2つ目は、日本のデジタル対応の落とし穴です。
第3章で、「日本が他国と比べてデジタル対応が遅れている理由」が2つ書かれているのですが、2つ目の理由に納得したので、紹介します。
2つ目の理由として挙げられていたのが、リアル接点でデジタルを活用するが、顧客接点の頻度が増やせないことケースが多いことです。
例えば「会員カードをデジタル化する」と考えたとき、顧客が店舗に来た時にデータを取ることができ、プッシュ通知などで一定の人にメリットがあるように見えます。
しかし、何も工夫しないと、店舗に行った時にアプリを開くだけで、それ以外ではアプリを開くことがないので、顧客接点が増やせないことになるのです。
僕の説明だと分かりにくいかもしれませんが、重要なのは、
対面で得られた信頼関係を、アプリなどの動線に誘導する。そこで得られたユーザの行動を、再度リアルなどで還元し、別のユーザアクションにつなげていくことです。
このように、デジタルだけで完結しようとせず、リアルとデジタルのそれぞれの強みを使って、相互に行き来できるようなUX(ユーザ体験)を作っていくことが必要だそうです。
1つ目の理由も書かれているのですが、気になる方はぜひ手に取ってご確認ください!
[第3位] DXの社内説得方法
そして、最後に1つ覚えておこうと思った話を紹介します。
なぜDXの社内説得方法を選んだかというと、今後、社内でDXを提案をするときに使えそうと思ったからです。
まず、大前提となるのが、以下2点が社内で共有できていることです。
①アフターデジタルという社会の中で、変化する状況に対応すべきであること
②DXとは、単なる効率化・コスト削減が目的ではなく、それに伴う新しいユーザ体験価値の提供が主な目的であること
以上の共通認識を揃える必要があります。ポイントとしては、DXはユーザ目線で考えること、ですね。
そして、次に「ビジネスモデル」と「会社にとっての活動の意味合い」の2つを説明する必要があります。
ビジネスモデルでは、現在あるコア事業を助ける役割となるのか、または単体でのスケールを狙っていくのか、などを考えます。著者は、前者を薦めており、単体では儲からないが、新たに顧客と関係を作っていく仕組みを構築することを考えましょう。
もう一つは会社にとっての活動の意味合いです。ここでは、DXの目的は新しいUXの提供なので、ビジネス的に成功するよりも、「バリュージャーニーの企画運用ができるようになること」を意識します。
詳細の説明は本を手に取って確認して欲しいですが、きっとDXの社内提案に関するヒントがあるでしょう。
『アフターデジタル2 UXと自由』は、アフターデジタルを読んで「読んでよかった」と思った方におすすめ
こんな方におすすめ
・アフターデジタルを読んで「読んでよかった」と思った方
・DXについて深く知りたい方
・データをどう戦略に活かすかを学びたい方
特に、アフターデジタルを読んで、読んでよかったと思った方は是非読んで欲しいです。
これからの時代に、DXをどう捉え、データをどのように利用していけばいいのかが具体的に書かれています。
逆に、下記のような人にはおすすめできません。
- アフターデジタルを読んでない方(アフターデジタルから読んだ方がいいと思います)
- DXについて興味ない方
アフターデジタルはこちらです
クチコミ

他の人がどう言っているかも気になるなー

著作権上、Twitterのコメントだけ紹介します。さらに気になる方は、Amazonレビューも参考にしてください!
プラスな意見
とプラスの意見が多く見られます!
デジタル関係の仕事をしている方は是非読んでおきたいですね!
マイナスな意見

プラスの意見だけでなく、マイナスな意見も参考にしてみてください!!
マイナス意見を載せようと思いましたが、なかなかマイナス意見を見つけることができませんでした。
人によっては、アフターデジタル1で十分だったというAmazonレビューもありました。
≫『アフターデジタル2 UXと自由』の口コミをAmazonで見てみる
まとめ
学べること
[第1位] OMOとO2Oの違いから学ぶ、OMOの真の目的 [第2位] 日本のデジタル対応の落とし穴 [第3位] DXの社内説得方法
おすすめの方
・アフターデジタルを読んで「読んでよかった」と思った方
・DXについて深く知りたい方
・データをどう戦略に活かすかを学びたい方
上記を聞いた上で、今回紹介した本をぜひ読んでみてください!
今回紹介した本
おまけ
現在、以下のサイトで無料で読み放題ができます!(無料期間に解約すればお金はかかりません)
★Kindle Unlimited | 30日間の無料体験をしてみる(期間終了後は月額980円、いつでも解約可) →本、マンガ、雑誌、写真集など合計200万冊以上が読み放題 ★Amazon Audible | 30日間無料+1冊無料キャンペーン →通勤などの移動中に本が聴けます


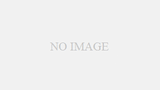


コメント