こんにちは、@ポジりすです!
「簿記2級受けることになったけど、どう勉強すればいいかわからない」と悩んでいませんか?
そんな方に向けて、「独学1ヶ月で合格した具体的な勉強スケジュール」について、記事を書きました!
まだ以下の記事を見ていない方は、先にそちらをご覧になることをおすすめします。

- 簿記2級を1ヶ月で合格できるスケジュール
- 簿記2級の勉強方法

こんな内容を紹介する記事を作成しました!
僕は現在社会人2年目で、2019年6月で簿記2級に合格しました。
本記事で紹介する勉強法を使えば、独学でも1ヶ月で合格できる方法を学べます!!
というのも、僕が大学生のときに、独学1ヶ月で合格したからです。

記事前半では1ヶ月のスケジュール、記事後半ではSTEP1~5までの進み方について解説します!!!
簡単な自己紹介をさせていただくと、僕は大学で経営学部に通っていました。多少、簿記3級程度の勉強をしたことがありましたが、簿記2級に挑戦する際は何もかも忘れていました。そんな僕でも独学で一発で合格できたメソッドについて紹介しています。
対象者
まず、以下の勉強法に挑戦可能な方を紹介します。
- 150〜200時間の勉強時間を確保できる方
- 少し努力して、できる限り少ない予算(5000円程度)で合格したい方
※お金に余裕のある方は、少し高いお金を払って通信で学習した方が圧倒的にいいです。効率よく最短で合格できると思います。
僕自身、簿記の工業簿記は通信で学習しましたが、最短でいい点数(9割)取ることができたので、おすすめです。
ただ、今回の記事ではできる限り少ない予算で合格したい向けに、自身の体験談と共に紹介します。
スケジュール
結論、僕のスケジュールでは、170時間程度の勉強時間を必要とします。社会人の方やゆっくり進めたい方でも、勉強スケジュールとして参考になるので、そのままご覧ください!
みなさん、人それぞれ学習時間はさまざまなので、5段階に分けて紹介します。
- Level 1 簿記3級学習 (目安:15時間)
- Level 2 商業簿記 基礎学習 (目安:15時間+11時間+9時間)
- Level 3 工業簿記 学習 (目安:20時間)
- Level 4 商業簿記 応用学習 (目安:12時間+8時間)
- Level 5 過去問&復習(目安:24時間+20時間+復習)
STEP1 簿記3級学習 (目安:15時間)

もうすぐ試験だけど、どこから手をつけていいかわからないよー

そうですよね、まず最初の1周目は簿記3級の内容から行いましょう!!
すでに簿記3級を受けた方でも、受けていない方でも、まずは簿記3級の範囲をざっと学習しましょう。
僕の場合、大学1年生で簿記3級の授業を受けてから3年経っていました。そのため、思い出すためにも、まずは参考書を1周しました。
おすすめの参考書は僕が使っていたこの本ですが、すでに参考書を買っている方はそちらで学習しても良いかと思います。
参考書を1周するポイントとしては、あまり時間をかけすぎないこと!!
わからなくても後で問題を解きながら復習できるので、最低15時間程度(3日ほど)で1周しましょう。
参考書を買うお金すらもったいないという方は、アカウンタンツライブラリーをおすすめします。こちらでは、簿記3級の講座を無料で提供していました。お金がない方はそれで学習してもいいかもしれません!
日商簿記3,2、経理の仕事に役立つ150以上の動画を学ぶサイト【Accountant's library】上記URLで「【キャンペーン】 日商簿記3級講座【第155回試験 対応】」を検索すると、表示されます。
このサービスは、後ほど行う工業簿記の学習でも利用するサービスですので、事前に登録してもいいと思います。
ここでのポイントは、
STEP 2 商業簿記 基礎学習 (目安:15時間+11時間+9時間)

ここからはSTEP2について紹介します!!
次に行っていくのが、商業簿記の学習です。商業簿記は、100点中60点を占め、ここを理解しなくては合格できない分野です。
内容としては、企業の経済活動を正確に計算し決算書を作成するなどを学習します。
今回、こちらのLevelでの勉強法を2つ紹介します。
- 参考書
- 通信
なぜ2つ紹介するかというと、僕が参考書で勉強した結果、通信で学習した方が効率面でかなり優れているなと感じたからです。
ただ、僕は商業簿記を参考書で勉強して合格しているので、そちらをメインに紹介します!
①参考書
まず紹介する勉強法は、僕が実際に行っていた参考書を使った勉強法です。
用意する参考書は以下の2つ。
このテキストは12章から構成されています。そして、各章ごとに基礎問題と応用問題が問題集に掲載されています。
勉強方法としては、テキストの1章ごとに、問題集の基礎問題を学習します。
目安時間としては、テキストを15時間程度。問題集の基礎問題を20時間。合計35時間を目安に学習してください。
ちなみに、テキストは12章あるため、1章1時間ペースです。
また、問題集の基礎問題は、問題の上に書いてある目安の時間に合わせて11時間で回答、復習の時間を9時間として計算しています。
このLevel2の段階では、完璧にするよりも、簿記の概要について理解できるといいです!!
②通信
2つ目の勉強法として、通信による学習を紹介します。
今回、できる限り予算を抑えたい方に書いている記事ですので、他のブログで紹介しているような高い通信は紹介しません。
一般的な、TACや資格の大原などの通信講座は5万以上かかってしまいます。
しかし、今回紹介する通信講座は月1000円以下です!!!
しかも、初月無料なので、1ヶ月で合格できればタダです!!!
日商簿記3,2、経理の仕事に役立つ150以上の動画を学ぶサイト【Accountant's library】特徴としては、
- 月額980円で受け放題(初月無料)
- わかりやすい内容
- 講座内容が幅広い
- テキストもダウンロード可能
勉強法としては、日商簿記2級講座(商業簿記)【第158回試験 対応】という講座を選択して、13時間程度の動画学習を行ってください。
おそらく、練習問題もあると思うので、計35時間程度で学習できるといいと思われます。
STEP2 のポイントとして、
STEP3 工業簿記 学習 (目安:20時間)

いよいよ、本番まで近くなってきました。気合入れて頑張っていきましょう!
STEP 3では、工業簿記の学習をしていきます。
工業簿記とは、企業の製造にかかる材料などを明らかにし、原価計算などを学習します。
工業簿記は、勉強すればするほど点が取りやすい、是非とも得点源にしたい範囲です。
僕が工業簿記を学習した方法は、先ほども紹介した通信講座です。
なぜかというと、商業簿記の参考書を勉強していく中で、動画で学習した方が効率よく学習できると思ったからです。そこで、工業簿記の勉強では、以下の動画学習サイトを登録し学習しました。
日商簿記3,2、経理の仕事に役立つ150以上の動画を学ぶサイト【Accountant's library】僕は、この通信講座の「日商簿記2級講座(工業簿記)【第158回試験 対応】」を受けていました。
大体15時間程度の動画学習となっていて、テキストに付随する問題を解けば終わりです。目安としては、20時間程度で学習しましょう!!
STEP3のポイントをまとめると、
STEP 4 商業簿記 応用学習 (目安:12時間+8時間)

あと少し頑張りましょう!
次に、商業簿記の学習に入る前に、過去問を1回解いてみましょう。
1回過去問を解いて、現在の実力がどうなのか確認してみましょう。そして、その実力度合いにより、どう学習すべきかについてご紹介します。
この後の学習としては、
- 60点以上→STEP4を飛ばして、STEP5に進む
- 30点〜60点→STEP4の商業簿記の応用問題に進む
- 30点未満→以前間違えた箇所を再度復習してから、STEP4に進む
STEP4では何を学習するのかというと、商業簿記の応用問題です。商業簿記はかなり深いところまで理解していないと、大問3で苦労してしまいます。
そのため、STEP2で紹介した問題集にある応用問題を使って学習していきます。
この応用問題は30題用意されているので、計画的に消化していきましょう。
時間の目安としては、問題の上に書いてある目安時間に合わせた計12時間で回答、復習8時間の計20時間としてください!!
STEP 4のポイントとしては、
STEP 5 過去問&復習(目安:24時間+20時間+復習)

さあ、最後です!頑張りましょう!
最後に、STEP 5で紹介するのは過去問を使った学習です。
僕が使っていた参考書は、こちらのTACが出している過去問題集です。
なぜこの本を選んだかというと、大問ごとに対策・テクニックがまとめられており、その後に12回もの過去問題集が掲載されているからです。(ネットに過去問は載っていません、、、、)
時間の目安としては、1回あたり2時間で解いて、2時間以内で復習してください。過去問が12回分ありますので、計50時間程度になります。
ただ、復習の際はあまり時間を意識せず、じっくり細部まで理解するようにしましょう。
ここまでできたら、あとは間違えた箇所をもう一度解いてみるなどして復習してください。
STEP 5のポイントとしては、
まとめ

いかがでしたでしょうか?今回紹介した勉強法を使えば、独学1ヶ月でも合格することは可能です。ただ、1日8時間勉強する必要が出てきたりと、なかなかハードな部分もあるので、できる人は余裕を持って準備すると良いと思います。
最後にもう一度内容を確認しましょう。
上記を意識して、今回紹介した参考書を使って合格を目指してください!!
皆様のお力に微力でも貢献できたら幸いです。
その際は、ぜひこちらのtwitterに報告いただけると嬉しいです。。。。
今回紹介した参考書
この記事を読んだ方におすすめの記事は、こちらです。
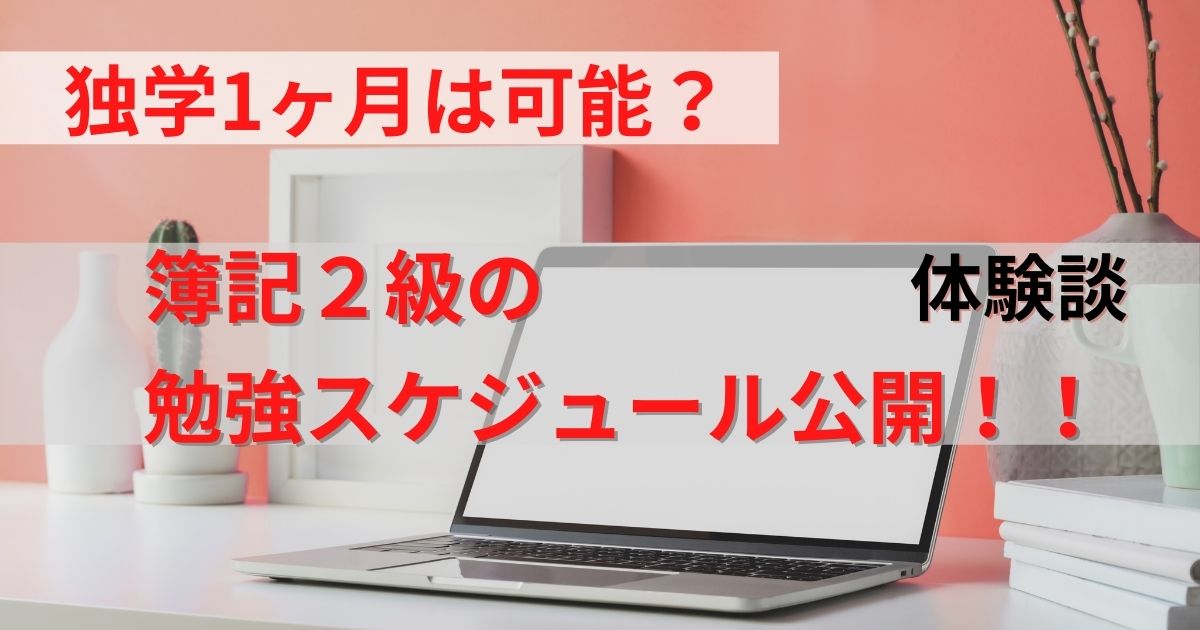
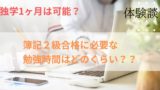




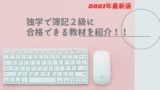
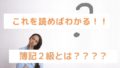
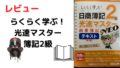
コメント